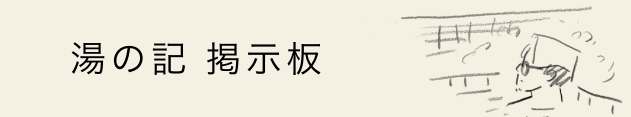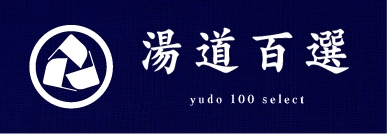2023
第二回「湯道文化賞」表彰式
表彰式 開催概要
日程:2023年11月5日(日)
場所:臨済宗大本山 大徳寺真珠庵
◆審査員
・小説家・エッセイスト/湯道文化振興会 理事 柏井 壽 氏
・温泉ビューティ研究家・トラベルジャーナリスト 石井 宏子 氏
・銭湯大使 ステファニー・コロイン 氏
・温泉カメラマン 杉本 圭 氏
・放送作家/湯道文化振興会 代表理事 小山 薫堂 氏
◆受賞者
湯道文化賞
入浴を「文化」へ昇華するために、特に輝かしい功績を遺した個人・団体。
長門湯本温泉 恩湯



<概要>
山口県で最も古い歴史を持つ長門湯本温泉は、応永34年(1427年)、
大寧寺の定庵殊禅禅師が住吉大明神からのおつげによって発見した「神授の湯」と伝えられる。
江戸時代には藩主も湯治に訪れ、浴室内に温泉神像を拝し、「恩湯」と呼称されたことからも、
人々の中に尊敬と感謝の心が受け継がれてきた湯であることが伺える。
施設の老朽化と利用客の減少により2017年5月に公設公営での営業を終了。
その後地域の若手たちが「長門湯守」を結成。2023年3月に再建した。
<受賞者コメント>
(長門湯本温泉 恩湯 大谷 和弘氏)
施設の老朽化や利用客の減少により2017年に公設公営での「恩湯」の営業は終了。
そこで「我々の手で地域の温泉を守っていこう!」と決意をしました。
そんななか、岩田方丈、鳴瀬宮司にご支援いただき、
このエリアで培われてきた歴史、文化、自然、物語、足元から「場所」を見つめ直し、
新しい恩湯の理念を元にこの事業をスタートいたしました。
また、理念を実現するにあたり、設計事務所岡昇平さんには、多大なるご尽力をいただきました。
これからも「温泉」というかけがえのない長門湯本の文化資本を地域や行政の皆様、
そして仲間とともに大切に守っていきたいと思います。
(長門湯本温泉 大寧寺方丈 岩田 啓靖氏)
大谷和弘さんのような若い担い手と下関市住吉神社の宮司さんと友情をわかちあって、
この場に立っているのは不思議な気持ちがいたします。
いろんな偶然が重なりましてこの喜びを共有しています。
(長門國一宮 住吉神社 宮司 鳴瀬 道生氏)
室町中期、当社の神様は、大寧寺の第三世住職・定庵殊禅に説法を受けに毎夜毎夜、
寺まで飛んで行き、その感謝の証として温泉の湧く場所を教えたと伝えられております。
それから600有余年、「恩湯」の名称が語り継がれている。
このことに価値があると、私は考えておりまして表彰式に出席をさせていただきました。
<講評>
(審査員:柏井 壽氏)
「恩湯」この字が全てを表していると思っております。私たちはつい源泉がどうか、
温度は何度か、泉質はどうかということばかり気にしてしまいますが、
本来、湯というものは神の恵みであり、地球から預かっているものだという認識をつい忘れがちです。
神様、仏様、そして我々人間が三位一体となって、この湯を大切に育てていく。
湯道が一番大事にしている湯はありがたいものだと、
はっきり思い出させてくれた「恩湯」を大切に育てている皆さんのお力だと思い、
文化賞を授与させていただきます。
湯道特別賞
入浴文化の発展・継続を支えてきた個人・団体。
栃尾又温泉


<概要>
奈良時代に開湯したという、1250年以上の歴史ある温泉。怪我や病気の療養の場、
半ば医療機関のような役目も担ってきた湯治場である。
江戸時代には湯守が存在し、佐渡から湯治客が来ていた。
現在、3軒の宿しかないが昔ながらの建物を大切にし、
一つの同じ共同浴場に浸かりに行く文化を残すことで、入浴者の交流を深めている。
<受賞者コメント>
(栃尾又温泉・自在館 星 宗兵氏)
代々の湯守たちが湯を継承してくれたおかげで、たまたま私がこの場に居させていただけています。
ご先祖様のおかげです。私自身、湯守を大変だと感じたことはありません。
むしろどうやったらより良い温泉に入っていただけるのかと考えることがとても楽しいのです。
たまたま温泉が湧く家に生まれ落ちたわけなので選べる道でもないでしょう。
3宿が共同で一生懸命、湯を守っていきたいと思います。
<講評>
(審査員:石井 宏子氏)
新潟県の栃尾又温泉は、江戸時代から続く歴史のある湯治(とうじ)場です。
その湯を守り続けていることはもちろん、なによりも授かった温泉をいかに使うかという点、
その素晴らしさも選考理由になりました。
栃尾又温泉の泉質は放射能泉で、ラジウム泉とも呼ばれ、加温したり、循環したりすると気化しやすい成分です。
栃尾又温泉の湯船のなかにはパイプが巡らせていて、その中には温かい湯が通してあり、湯をうめることなく温めて、
湯船の中の感じる温度がすべて一定に保たれています。
35度のぬるい人肌の湯に入っていますとだんだんと無重力のような無の境地に誘われてきます。
そうした素晴らしい空間を工夫で創り出していることに感動いたしました。
これからも3宿が協力し合ってひとつの共同浴場の湯を守っていただきたいです。
中乃湯


<プロフィール>
1933年沖縄県生まれ
1958年 現在では沖縄唯一となる銭湯「中乃湯」を現在の地に移転・創業
1970年 仲村家に嫁ぎ、夫とともに「中乃湯」を経営。
1984年 夫が急逝。
2023年 新しいスタッフが参画。15年ぶりに夜の営業を開始。
<受賞者コメント>
(中乃湯 仲村シゲ氏)
「なんともいえないねー。ゆーふるやー(風呂屋)で、そんな大層なことをしたかなーと思うけどね~。
賞状は上等さー。最高な気持ち、最高さー。こんな素敵な賞をくださった、
湯道文化振興会の小山薫堂さんという方にお礼を言わないといけないね」
<講評/湯道文化振興会>
中乃湯は沖縄に一軒だけ残る日本最南端の銭湯です。
90歳になる仲村シゲさんは、50年近くおひとりで銭湯を守ってこられました。
沖縄の方言で「ゆんたく」と呼ばれるお客さんとのおしゃべりを日課とし、
ときには三線さんしんに合わせて歌をうたい、
仲村さんのお人柄によって地域の方々の体と心を温め、沖縄の銭湯文化を守り続けています。
湯道工芸賞
入浴関連の道具や建物を制作するとともに、それらの国内外への魅力発信に寄与した個人・団体。
おぼろタオル株式会社


<概要>
1908(明治41)年、三重県津市で創業。朧染タオル製造の特許を取得。
1927(昭和2)年に”ガーゼタオル”を製造・販売し現在に至る。
「タオル製造一貫作業工程」にこだわり、「一度使ったら忘れられない心地よい風合い」を実現している。
<受賞者コメント>
(おぼろタオル株式会社 森田 壮氏)
まさかこんな賞をいただけるなんていうのも夢にも思っていなかったものですから、
お話いただき従業員一同、本当に喜んでおります。
1908年に私の曾祖父でもあり日本画家でもあった森田庄三郎が
ヨコ糸だけが染まる〈おぼろ染め〉という特殊技術を開発し、以来115年、
多くの方の力を得て、日本の入浴文化に寄り添った形のものづくりをひたすら続けてこれたことに感謝しております。
これからも入浴文化の発展に寄与できるよう、ものづくりを続けていきたいと思っております。
<講評>
(審査員:杉本 圭氏)
講評/温泉カメラマン 杉本 圭氏
温泉を撮るという仕事に携わって20年以上が経たち、仕事柄、いろいろなタオルを使ってきました。
おぼろタオルの良さというのは、まず濡れることによって発色が良くなり鮮やかに模様が浮かび上がってくる。
そして驚くほどの吸水性が良く、乾きも早い。そして何より軽い。そうした素晴らしいタオルに敬意を表します。
湯道創造賞
これまでにない発想や取り組みで、入浴に新たな価値を付加している個人・団体。
銭湯建築家 今井 健太郎氏


<プロフィール>
1967年静岡市生まれ。92年武蔵野美術大学大学院造形研究科修了後、
アトリエ設計事務所に勤務。20代後半より風呂なしアパートに住み銭湯暮らしを始める。
近隣の銭湯を毎日利用しているうちに銭湯ファンとなり、都内各地の銭湯巡りを始める。
98年今井健太郎建築設計事務所設立後、銭湯/温浴施設を中心としリサーチ/設計/イベント企画などの活動を始める。
伝統的かつ現代に生きながらえる銭湯空間を提案し都内銭湯をはじめとする温浴施設の設計実績に繋げてきた。
著書に『銭湯空間』(KADOKAWA)がある。
<受賞者コメント>
(銭湯建築家 今井 健太郎氏)
「日本人が長く親しんできた銭湯という生活文化が廃れてしまうのはあまりにも勿体無い。
銭湯がある生活をもう一度現代に復活させ、そして未来につなげたい」と、
そのような思いから、銭湯に関わる設計活動をスタートいたしました。
そうした私どもの活動を評価していただき、また湯道文化振興会様の趣旨との共通性を
感じていただけたことを大変嬉しく思います。
今後も湯空間の設計を通じた私どもの活動が日本の湯文化継承、発展への貢献となるよう一層励んでまいります。
<講評/湯道文化振興会>
今井さんは東京都の「はすぬま温泉」、青森県の「桂温泉」、
山形県の「湯るりさがえ」など日本全国の温浴施設を手がけていらっしゃいます。
お風呂の地域固有の歴史、文化、気候風土などといった様々な背景を踏まえて、
湯の空間設計されていること。身体的なものだけでなく、
精神的にも何かとの一体的感覚を感じる場として捉えていらっしゃるところが「湯道」と合致しています。
創意工夫しながら、湯空間を設計されていることが受賞の理由となりました。
湯道貢献賞
「湯道」の精神理念に深く共感し、それを体現する個人・団体。
在京都フランス総領事館


<概要>
フランスが京都府京都市に設置している総領事館。
1858年の日仏修好通商条約締結以来、総領事館うを日本国内に設置。
2009年それまで大阪市にあった西日本を管轄する在大阪・神戸フランス総領事館が
関西日仏学院内に移転。現在の総領事はサンドリン・ムシェ氏。
日本文化に精通し、湯道を理解くださり、2023年4月、関西日仏学館にて『湯道展』の開催に至った。
<受賞者コメント>
(在京都フランス総領事館 文化部長芸術部門主任 ジュリエット・シュヴァリエ氏)
2023年4月、関西日仏学館にて開催された『湯道展』に来場された方々に、
日本のみならずフランスの入浴文化をも伝えることができましたことを嬉しく思います。
日本にお風呂のための道具がたくさんあるということ、
その職人技や銭湯や温泉の建築物の美しさが印象に残っています。
フランス人の日本に対する関心は高く、来日するフランス人もますます増えています。
湯道を通じ日仏交流の発展も期待しています。
<講評>
(審査員:銭湯大使 ステファニー・コロイン氏)
私はフランスから15年前に来日し、日本固有の銭湯文化とそこに集まる人々の温かさに触れ、
この素晴らしい文化を広めたいという熱い願望を抱きました。
関西日仏学館での湯道展は、日仏の風呂文化の交流となり、湯道を世界に広げるきっかけづくりとなりました。
これからも日仏の風呂文化の交流ができることを期待しています。